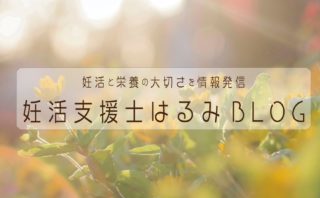妊活支援士はるみです。
受精卵が着床しない原因のひとつに、ミトコンドリアが関係していると言われています。
その理由は、ミトコンドリアが受精卵の成長(成熟・細胞分裂)に関係しているから。
つまり、ミトコンドリアを活性化できれば、妊娠力が上がることが期待できます。
ミトコンドリアとは
ミトコンドリアは、ヒトのすべての細胞に存在する「小器官」です。
一番大きな働きは、酸素と栄養を使って、私たちの生命活動に使われるエネルギーを作りだすこと。
このエネルギーは、消化・吸収、吸収した栄養の合成、細胞分裂、核酸の合成、筋肉の収縮などのあらゆる生命活動に関わっているのです。
身体で使われるエネルギーの約90%が、ミトコンドリアで作られます。
つまり私たちが日々元気に生きられるかどうかは、ミトコンドリアが細胞内にどれだけいるか、ということに左右されるのです。
エネルギー生産のほかにも、古い細胞が新しいものに入れ替わる、アポトーシス(細胞死)という働きや、細胞内のカルシウムイオン濃度の調節、脂質の酸化、免疫反応にも関係しています。
卵子とミトコンドリア
人体の細胞の中でミトコンドリアが一番多いのが、卵子です。
たったひとつの細胞が、60兆ともいわれる数になるほど細胞分裂をするのですから、たくさんのエネルギーが必要になります。
ところが、老化によって卵子のミトコンドリア数は少なくなると言われています。
卵子が老化すると妊娠しづらくなる、と言われるのは、実はミトコンドリアが関係しています。
というのも、ミトコンドリアの数が少なくなると、卵子が成熟しづらかったり、細胞分裂が遅くなるのです。
想像してみてください。
小学生の時、ホウセンカという植物の種を触ったことがありませんか?
ホウセンカは、種が十分成熟すると、少しでも遠くに飛ばすため、黒い種がはじけ飛ぶのです。
しかし、種が十分成熟していないとはじけないし、中を開けてみてもまだ白いままだったりします。
未成熟な種は、そのまま植えても芽が出ないか、芽が出ても他の種に比べて育ちが悪くなります。
卵子もホウセンカのように、十分成熟したものが卵巣から飛び出してきます。
卵子が成熟しないと、排卵がなかったり、排卵しても受精→分裂→着床→成長できる生命力がなかったりします。
また、受精卵が着床できるのは、「胚盤胞」という段階まで成長している必要があります。
「胚盤胞」になって初めて、子宮内膜に根を張ることができるのです。
細胞分裂が遅いと、子宮にたどり着いた時にはまだ「胚盤胞」まで育っておらず、着床できないまま流れてしまうことになります。
近年、受精卵の着床位置が下にずれることを指す、「前置胎盤」という妊娠状態の発症率が高くなっているのは、細胞分裂が遅いことも一因になっていると考えられます。
「前置胎盤」の場合、流産や早産の確率が高くなるため、できれば避けたい状態。
この卵子の成熟や受精卵の細胞分裂に必要なエネルギーは、すべてミトコンドリアで作り出されます。

精子とミトコンドリア
精子はおたまじゃくしのような形をしています。
そのしっぽ(鞭毛)を動かして、泳ぐように奥へ進んでいくのですが、その際の運動エネルギーの供給は、精子の首の根本にあるミトコンドリアです。
ダイビングをするときに背負う酸素ボンベをイメージするといいかもしれません。
酸素が足りないと目的の場所まで潜れないのと同じように、このミトコンドリアがしっかりエネルギーを作れないと、卵子にたどり着く前に力尽きてしまいます。
また、受精した後、DNAを放出した精子の残骸は、分解、吸収され、受精卵の栄養になるそうです。
せっかく栄養になるなら、精子のミトコンドリアの質もしっかり上げておきたいですよね。

卵子や精子の「質を高める」ために
こういう話を聞くと、「いい卵子」や「いい精子」を作るために、ミトコンドリアをできるだけ減らしたくないと思いませんか?
そう思ったら、まず食習慣から見直してみましょう。
例えば糖質過多な食事や偏った食生活では、エネルギーを生成する際に必要な栄養が足りないため、ミトコンドリアは減ってしまいます。
また、ミトコンドリアは酸素を使うため、活性酸素から守る必要もあります。
つまり、栄養をバランスよくしっかり摂る、抗酸化作用のあるものを摂る、これだけでも、ミトコンドリアの数が増える(あるいは維持できる)ことになるのです。
普段の食生活だけではなかなかカバーしきれない栄養素。
妊活支援士が提案する、EUの特許を80以上取得している栄養機能食品は、あなたの身体のミトコンドリアを応援する栄養が詰まっています。
栄養が足りない不安感を手放し、栄養が足りている安心感を体感して、妊活に臨みましょう!